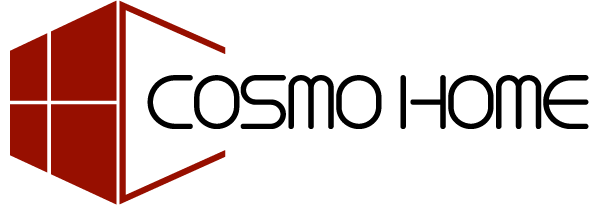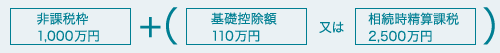家づくりを考えた時、多くの方は、融資を受けます。
そのため、住宅ローンは避けて通れない問題です。
そこで、少しお金のお話をしていこうと思います。
最初に、家づくりに大切なことは、先ずは健康であるということです。
基本的に、健康でないと住宅ローンは借りられません。
というのも、銀行で住宅ローンを借りる際は、債務者は団体信用生命保険に加入しなければなりません。
ようするに、債務者が返済途中で不幸にも亡くなったり、重大な心身の病気になった時に、保険で本人の代わりに、住宅ローンを返済する仕組みになっています。
その保険が団体信用生命保険です。
通常、銀行ローンの場合、保険料は、皆さんが借りる金利の中に含まれていますので、改めて支払う必要はありません。
但し、住宅金融支援機構が貸付するフラット35は、年一回保険料を支払います。
しかし、絶対に健康でないと借りられないかというとそうでもないのです。
その方法は二つあります。
①連帯債務者が加入できれば可能(持分は相談要)
②フラット35は保険加入が義務ではないので融資可能
このように、ローンは借りられますがやはり注意が必要です。
というのも、保険加入されていない方が亡くなった場合、融資住宅を相続された方が住宅ローンを引き継ぎ返済していかなければなりません。
すなわち、残された家族に負担を残すことになります。
このようにならないように、やはり団体信用生命保険には加入しておくべきだと思います。
ようするに、家づくりは何時でもできものではなく、ある程度の若さと健康が必要だということです。
ちなみに、融資を受ける年齢制限は、
借り入れ時:満20歳以上66歳未満であること(団体信用生命保険に加入できる年齢は借り入れ時20歳以上71歳未満)
最終返済時:原則、満82歳未満
となっています。
借金と言えども誰でもできる訳ではないのです。
by kakizaki