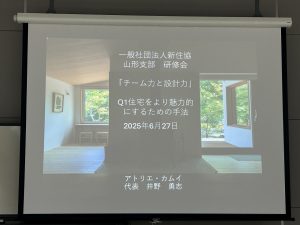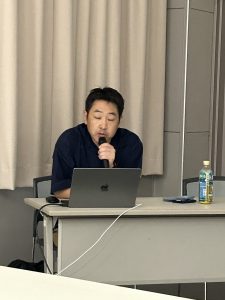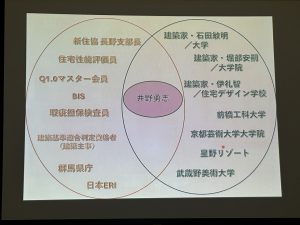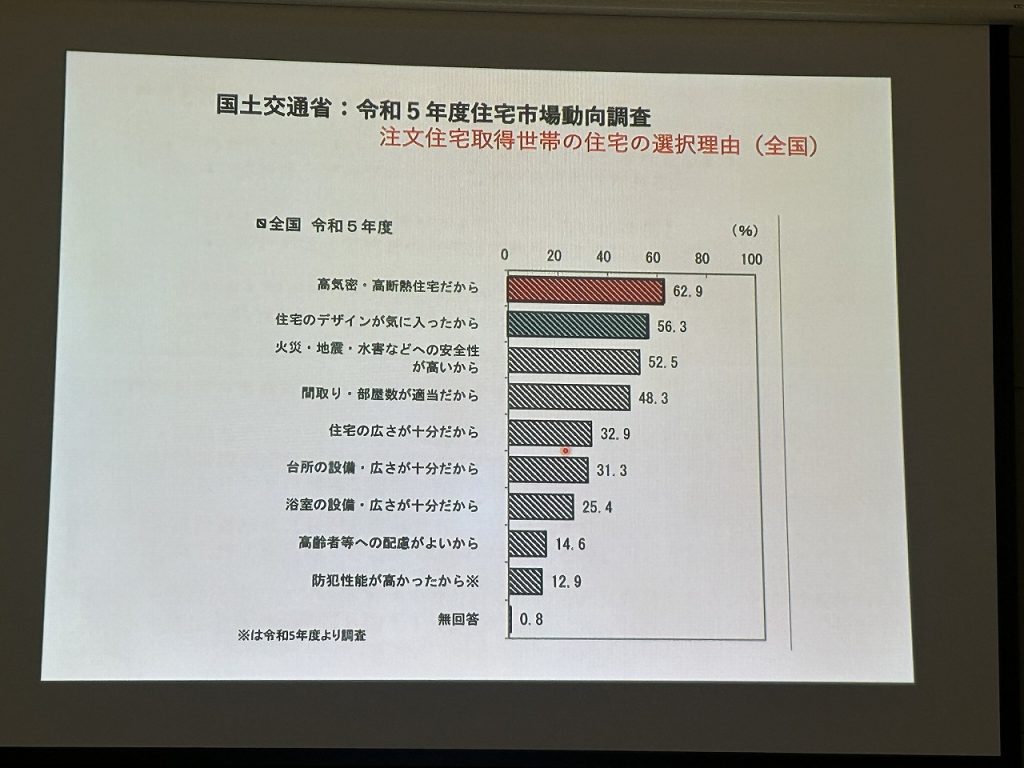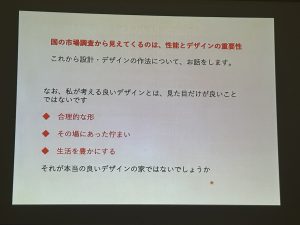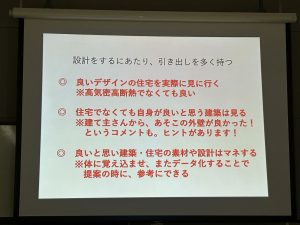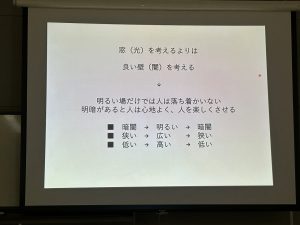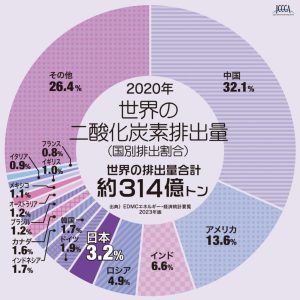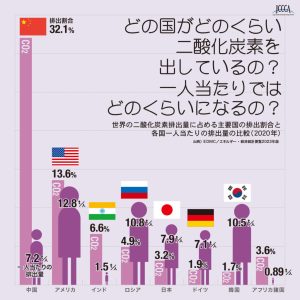昨年の元旦に能登半島に地震があってから丁度一年が経ちました。
お正月の間、あちこちのテレビ局で現況を伝える報道番組を見ましたが、なかなか復興が進んでいないのが現状のようです。
1月4日の山形新聞に「自宅耐震化」の事が記事に載っていました。

日本世論調査会のまとめによると、耐震化は48%という結果だったそうです。
即ち、約半分の人は、耐震性に難がある住宅に住んでいることになります。
日本の耐震基準は、年代によって次のように変遷してきました。
建築基準法が1950年に制定され、それ以降の建物を三つの基準に分けています。
(震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと)
(中地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと)
(震度6強から7程度に対しても倒壊や崩壊しないこと)
新耐震基準以降が、一応、耐震化された建物と言えます。
酒田市では、毎年、「酒田市木造住宅耐震診断士派遣」制度(本人負担15,000円図面あり)を実施し、災害に強い街づくりを目指しています。
この制度では、2000年5月以前の建物、即ち、新耐震基準の建物も調査対象になっています。
これは、1995年に起きた阪神淡路大震災の際に新耐震基準の建物でも倒壊する恐れがあることが分かったからです。
また、2016年の熊本地震では、4月14日と16日に震度7の大きな揺れが、2回連続して発生するという今まで想定していなかったことが起こりました。(※従来は、建物が受ける大きな地震は、一回と想定)
このようなことからも、新耐震基準でも決して安全とは言えないのが現状です。
現在住んでいる建物の新築年数が2000年6月以降か是非確認して見てください。
もし、それ以前でしたら、耐震診断を受ける事をお勧め致します。
「酒田市木造住宅耐震診断士派遣」は、酒田市広報の年度最初の頃に掲載されます。






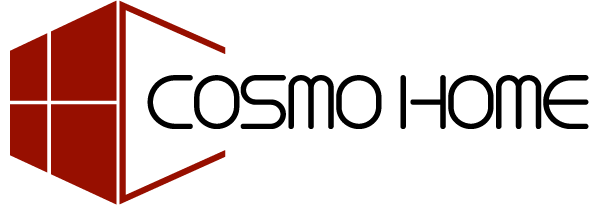

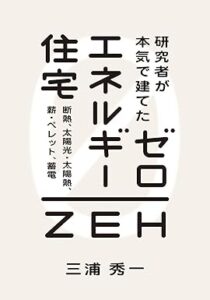
_page-0013-1024x576.jpg)
_page-0008-1024x576.jpg)