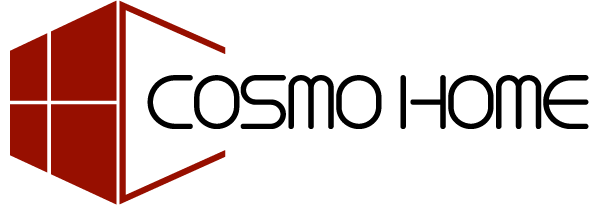「太陽光発電は必要ですか?」
お客様と打ち合わせしていると良く尋ねられる質問です。
巷では、
ZEH(ゼッチ)住宅【経済産業省】
ゼロエネルギー住宅【国土交通省】
と言う名で、補助金目当てに色々宣伝されています。
上記の二つの政策とも、太陽光発電を設置することが、絶対条件になっているので、太陽光発電ありきで量産ハウスメーカーでは、住宅販売を促進しているようです。
ここは、ちょっと待って頂きたいのです。
多くの量産ハウスメーカーは、建物の断熱性能は、最低基準をクリアする程度で、後は、出来るだけ太陽光発電で、賄うタイプが多いのです。
この種の住宅は、建築の価格を押さえられ、尚且つ補助金を受けられるということで、営業的には、やり易いものになります。
しかし、このような住宅は、ゼロエネルギーとは、名ばかりで、省エネ的には思ったより成果を上げていないことも分かってきました。
私たちが目指す住宅は、まず最初に断熱性能を十分に上げた建物です。
その性能の一つの基準になるのが、弊社ではQ1.0(キューワン)住宅クラスと考えています。

上記のように壁の外側にグラスウール16kgを100mm充填したり、高性能サッシや、換気を工夫することで、概ね熱損失係数Q値が1.0に近い数字になります。
このレベルは、国が2020年までに断熱性能を義務化するQ値=2.4の約2~3倍の高性能な住宅です。
私たちは、もし太陽光発電設備を設置するのであるならば、まず、このレベルまで建物性能上げて、必要最低限のパネルを小資金で設置するのがいいと思っています。
今年1月27日(金)引き渡した、酒田市光ヶ丘の家づくりのテーマが、
『リビング越しにつながる広いテラスがある家』


のオーナー様は、
「太陽光発電はいらないね」
と仰っていました。
「光熱費は、暖房含めそれ程負担にならないね。あえて設備費にお金掛ける必要もないように思う。」という感想でした。
ここから先の設備は、私は、各自の判断でいいと思っています。
太陽光発電ありきの国の政策は、いかがなものかと、いつも疑問に思っています。
国民の私達にもっと選択の幅を利かせて頂きたいと思いますね。