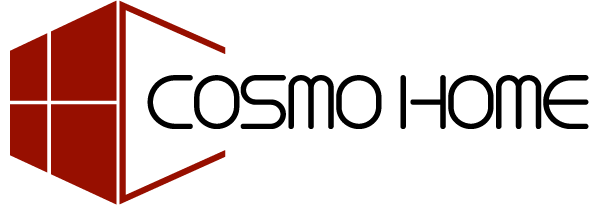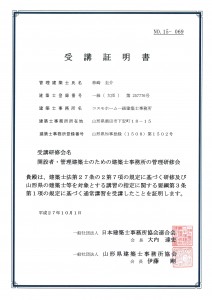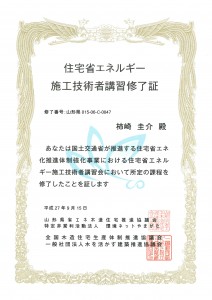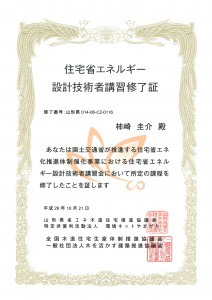鶴岡市桜新町に建設中の
テーマが、
「借景を見ながら四季を感じる家」
の写真撮りに行ってきました。
天気がいい日は、写真撮りが気になってどうしようもありません。

こげ茶色の外壁とポーチ廻りの木の配色の組み合わせがとても似合います。

道路沿いの赤い植物の名前がちょっと分かりませんが、とても綺麗です。

車二台が入るビルトインガレージになっています。

建物の周りは、自然がいっぱいで、写真左は、八重桜の並木になっています。
鶴岡公園に咲いているソメイヨシノより、1~2週間程度遅く咲くのが特徴で、土手沿いに並んでいます。



伊藤のブログでも紹介していました、ルイスポールセン社の『PH5』のペンダント照明がこのリビングの中心になっています。
照明一個で、こんなにも雰囲気が変わるもんですね。





何と言っても、この住宅は二階リビングの大きな窓からの借景が見どころです。

鶴岡のシンボルの金峰山が、こんな形で見られるとっても贅沢なロケーションです。
完成内覧会は、11月14日(土)、15日(日)の二日間です。
後日、ホームページ上でもご案内致します。
どうしても当日、ご都合の悪い方は、事前にご連絡頂ければ、個別にご案内致します。